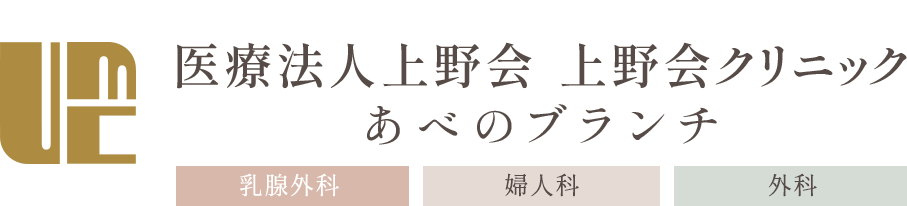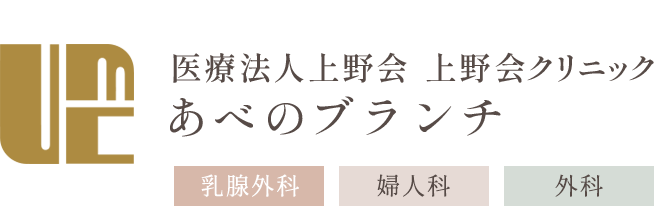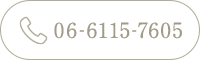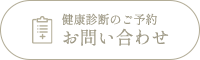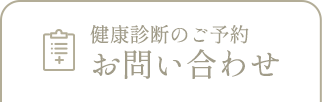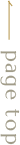月経困難症
 月経困難症とは、月経に伴う下腹部痛や腰痛、吐き気、頭痛などの症状によって、仕事や学校などの日常生活に支障をきたす状態を指します。
月経困難症とは、月経に伴う下腹部痛や腰痛、吐き気、頭痛などの症状によって、仕事や学校などの日常生活に支障をきたす状態を指します。
女性の多くが月経痛を経験していますが、症状が重くても受診せず我慢している人が多いのが現状です。
月経困難症の原因
月経困難症の原因は、器質性月経困難症と機能性月経困難症の2つに分けられます。いずれの場合も、プロスタグランジンという痛みの原因物質の分泌が関係しています。また子宮口の狭さやストレス、冷え、運動不足などが影響すると言われています。
器質性月経困難症
子宮筋腫や子宮腺筋症、子宮内膜症などの子宮や卵巣に病気があることが原因で起こります。過多月経や性交痛、排便痛を伴うことがあります。
機能性月経困難症
子宮や卵巣に明らかな異常がないにもかかわらず、痛みを強く感じる状態で、若い人に多く見られます。原因としては、プロスタグランジンの分泌過多や子宮頸管が狭いことなどが挙げられます。
月経困難症の症状
下腹部の痛みや腰痛など一般に月経痛と呼ばれるものが主な症状ですが、それに加えて下記のような症状が出ることがあります。
- 腹部の張り
- 悪心(吐き気)
- 頭痛
- 疲労感・脱力感
- 食欲が出ない
- イライラしやすくなる
- 下痢
- 憂うつ
月経困難症の検査方法
月経困難症の原因に器質性の疾患がないかどうかを調べるため、経腟超音波検査や腹部または経直腸エコーを実施し、子宮内膜症、子宮腺筋症、子宮筋腫などがないか確認します。また必要に応じて尿検査により妊娠の有無を調べたり、血液検査を行います。
月経困難症の治療方法
器質性月経困難症であると分かった場合は、原因疾患の治療を行います。疾患によっては手術が必要なこともあります。
機能性月経困難症と診断された場合は、鎮痛剤や鎮痙剤などで対症療法を行います。低用量ピル、黄体ホルモン製剤でホルモンバランスを整えたり、抗不安薬、漢方薬を処方したり、温熱療法を指導する場合もあります。
月経前症候群(PMS)
 月経前症候群(PMS)とは、月経の1〜2週間前から始まる精神的・身体的な不調の総称です。月経が始まると自然と症状が治まります。症状には個人差があり、日常生活に支障をきたすほど強い場合にPMSと診断されます。
月経前症候群(PMS)とは、月経の1〜2週間前から始まる精神的・身体的な不調の総称です。月経が始まると自然と症状が治まります。症状には個人差があり、日常生活に支障をきたすほど強い場合にPMSと診断されます。
日本では約70〜80%の女性が何らかの症状を感じており、約5.4%は生活に支障があるレベルの症状に悩まされています。症状が3ヶ月以上続いているかどうかが月経前症候群(PMS)の診断の目安となります。
月経前症候群(PMS)の原因
⽉経前症候群(PMS)の原因は、明確には解明されていませんが、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの変動が、脳内ホルモンや神経伝達物質に影響を及ぼしていると考えられています。実際に月経前症候群の患者は月経直前にセロトニンの分泌量が低下していることが報告されています。
また間接的な要因として、食事や生活習慣の乱れ、ビタミンB6の不足が影響していると言われています。
月経前症候群(PMS)の症状
⽉経前症候群(PMS)で起こる症状は200とも300とも言われており、人によって症状は異なりますが、一般的には下記のような症状が挙げられます。
身体的な症状
- 腹痛、頭痛、腰痛
- お腹が張る
- 肌荒れやニキビ
- 胸が張る
- むくみが出る
- 便秘
- 不眠や日中の眠気
- 疲れやすくなる
- 食欲がなくなる
- 便秘
- むくみが出る
- 過食
精神的な症状
- 怒りっぽくなる
- 気分が落ち込んだり、憂うつになる
- 不安を感じやすくなる
- 落ち着かず、そわそわする
- 集中力が続かなくなる
- やる気が出にくくなる
- 涙が出やすくなる
月経前症候群(PMS)の検査方法
月経前症候群(PMS)の診断には明確な検査や基準はありません。毎月、月経前に症状が現れ、月経が始まると軽快するという特徴に注目して判断されます。そのため、症状の出現時期と月経周期との関係を記録することが診断の手がかりとなります。あわせて、PMDD(月経前不快気分障害)やうつ病などの精神疾患でないかどうかを見極めることも重要です。
月経前症候群(PMS)の治療方法
月経前症候群(PMS)は排卵によって起こるホルモンバランスの変化が原因のため、低用量ピルや低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬によって排卵を止めることで症状が抑えられます。
ただし症状が軽い方や服薬を最小限にしたい方に対しては、鎮痛剤などを処方して対症療法を行うこともあります。
月経前症候群(PMS)を和らげる方法は?
生活習慣や食事の乱れなどが症状を悪化させる場合があります。以下のポイントに注意して取り組んでみましょう。
適度に運動する
ウォーキングやジョギング、水泳といった有酸素運動をはじめ、適度な運動が効果的です。
規則正しい生活をする
規則正しい睡眠習慣を保ち、毎日同じ時間に寝起きすることを意識しましょう。入浴やマッサージは快眠を助けてくれます。
喫煙や飲酒を控える
喫煙や飲酒は症状を悪化させると言われています。特に喫煙は女性ホルモンの働きを弱めると言われていますので要注意です。
食生活の見直し
栄養バランスの偏った食事が、症状を悪化させる要因になります。特に下記の栄養素が不足しないよう、意識して食事を摂りましょう。
たんぱく質(肉・魚・大豆製品)
神経伝達物質のセロトニンの材料となるため重要です。
マグネシウム(海藻・魚介・豆類)
精神的な症状やストレスを和らげる作用があり、不足すると不整脈や抑うつなどの症状が現れると言われています。
カルシウム(乳製品・大豆製品)
むくみやイライラを和らげると言われています。ビタミンDを摂るとカルシウムの体内への吸収率が高まります。
ビタミンB₆・E(赤身の肉・魚・ナッツなど)
ビタミンB6にはむくみや肌荒れの予防、女性ホルモン活性化などの効果があると言われています。またビタミンEはむくみや精神的な症状を軽減すると考えられています。
反対に糖質や塩分、カフェインは取りすぎると症状を悪化させるリスクがあると考えられています。適切な量であれば問題ありませんが注意しましょう。
一人でストレスを抱え込まない
仕事や家事、育児などのストレスは症状に大きく影響します。趣味や友人・家族との時間などでリフレッシュする時間を設けましょう。
またパートナーや家族などに、どういった症状が出るかを共有しておき、あらかじめ理解してもらうのもおすすめです。協力しながら、症状と上手に付き合っていきましょう。
つらい症状がある時には、一人で抱え込まずに、上野会クリニック あべのBranchへご相談ください。