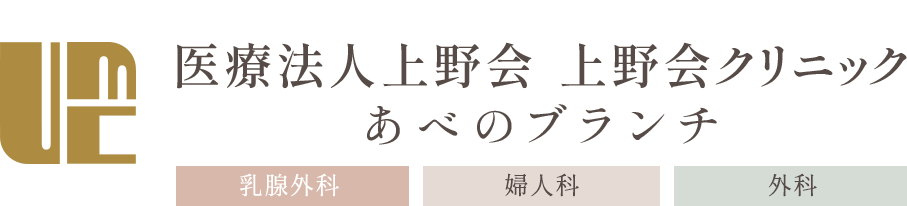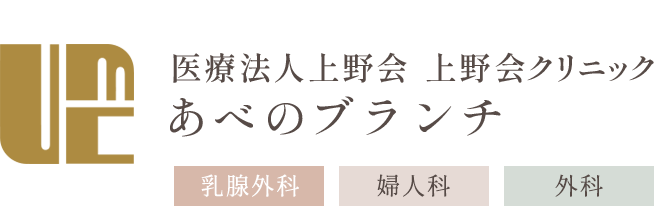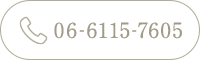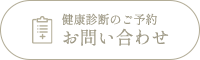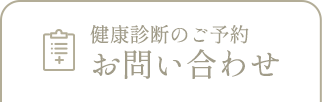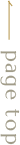不正出血とは
 不正出血とは、生理以外のタイミングで性器から出る血のことです。婦人科を訪れる理由の中でもよく見られるものです。血の色は真っ赤なものから、茶色や赤褐色、ピンクや黄色、黒っぽいものまで多彩です。量も多い場合や、ごく少量の血がおりものに混ざる程度の場合もあります。
不正出血とは、生理以外のタイミングで性器から出る血のことです。婦人科を訪れる理由の中でもよく見られるものです。血の色は真っ赤なものから、茶色や赤褐色、ピンクや黄色、黒っぽいものまで多彩です。量も多い場合や、ごく少量の血がおりものに混ざる程度の場合もあります。
不正出血の原因
 過労やストレス、更年期によるホルモンの変動、無排卵などによる女性ホルモンの低下が原因となることがあります。また、子宮や膣、卵巣の病気、妊娠に関わる異常など、多くの病気が原因となることもあります。
過労やストレス、更年期によるホルモンの変動、無排卵などによる女性ホルモンの低下が原因となることがあります。また、子宮や膣、卵巣の病気、妊娠に関わる異常など、多くの病気が原因となることもあります。
不正出血のセルフチェック
不正出血には様々なタイプがあり、判断に迷うこともあります。以下の項目に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
- 下着に少量の血がついている
- 茶色いおりものが出る
- 生理以外の時期に鮮血が出た
- 生理以外の日に出血し1日で収まった
- 閉経後に出血があった
- 痛みやかゆみを伴う出血がある
1つでも当てはまれば、不正出血の可能性が高いです。特に閉経後の出血や痛み・かゆみを伴う出血があれば上野会クリニック あべのBranchへお早めにご相談ください。
不正出血と生理の違い
 生理不順の出血は、子宮内膜が剥がれ落ちて起こる点で通常の生理と同じです。
生理不順の出血は、子宮内膜が剥がれ落ちて起こる点で通常の生理と同じです。
一方、不正出血は子宮や膣、卵巣、時には尿道や肛門など別の場所から出血している可能性もあります。
生理不順かどうか迷う場合は、基礎体温をつけてみましょう。排卵があれば体温に明確な変化が見られます。判断が難しい時は、婦人科でグラフを確認してもらうと安心です。
不正出血を引き起こす病気
不正出血には子宮や卵巣などの病気が隠れている可能性があります。
子宮の病気
下記のような子宮の病気で不正出血が起こることがあります。
子宮筋腫
子宮にできる良性のしこりで、30代以降に多い病気です。大きくなると強い生理痛や不正出血を引き起こします。
子宮腺筋症
子宮平滑筋という筋肉が厚くなる病気です。40代の出産経験者に多い傾向があります。不正出血や腰痛を伴い、不妊の一因となることもあります。
子宮内膜増殖症
子宮内膜が過剰に増える病気で、放置するとがん化することもあります。ホルモン異常が主な原因です。
子宮頸がん
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染が原因で起こるがんです。不正出血や性交時出血、下腹部痛が見られます。
子宮腟部びらん
子宮腟部がただれて見える状態のことを言います。10〜30代に多く、不正出血や痛み、おりものの変化が現れます。がんとの鑑別が重要です。
卵巣の病気
卵巣の病気の中にも、不正出血するものがあります。
卵巣腫瘍
卵巣にできる腫瘍で、年齢を問わず発症の可能性があります。良性・悪性があり、下腹部痛や頻尿、腹部の張りが症状です。肥大すると破裂して大量出血することもあります。
卵巣機能不全
卵巣の働きが低下する病気で、10〜50代と幅広い年代で発症します。ホルモン分泌の乱れにより、不正出血や生理不順、無月経を引き起こします。
膣の病気
膣が炎症を起こすなどして出血する場合もあります。
萎縮性腟炎
閉経後にエストロゲンという女性ホルモンが減少し、腟や外陰部の粘膜が弱くなることで起こる炎症です。出血しやすく、不正出血の原因になります。
不正出血どのくらい続いたら病院に行くべき?
不正出血は、生理以外の出血という時点で異常のサインです。下腹部痛や経血量の増加を伴う場合は、婦人科系の病気の可能性が高まります。
周期が不安定で生理かどうか判断できない場合でも、まずは婦人科へ相談しましょう。
不正出血の検査方法
 不正出血の原因を特定するためには、主に下記のような検査を行います。
不正出血の原因を特定するためには、主に下記のような検査を行います。
妊娠反応検査
尿検査で妊娠していないかを確認します。
血液検査
ホルモン量や貧血がないかを確認します。
おりものの検査
細菌の種類・量や性感染症がないかを調べます。
超音波検査(エコー)
子宮や卵巣に腫瘍などの異常がないかを確認します。
がんの検査
子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸がん・子宮体がんがないかを調べます。
不正出血の治療方法
不正出血の原因が確認できたら、その原因に対してアプローチします。例えば、ホルモンの乱れが原因であれば、軽度なら生活習慣の改善で様子を見ます。長引く場合や貧血を伴う場合は、ホルモン剤を処方してホルモンバランスを調整します。
ポリープやがんだった場合は、手術や薬物療法などの治療方針を医師と相談しながら決定します。
性感染症などの炎症が原因の場合は、抗生剤などで治療を行います。